特長
寸法安定性、精度が
極めて高い製品です
ロータリーレースで切削することで、流れ節や低質材部を除去することができ、単板乾燥によって含水率の分布を均等化させ、さらに積層接着によって節など欠点部分の分散が行われるため、寸法安定性、精度が極めて高い製品です。
長尺通直材が得られます
小径木や曲がり材、間伐材など短い丸太からでも、単板を縦つぎにして連続することにより、長尺の製品が得られます。また、縦つぎ部の位置を層間毎に分散させることによって、製品強度を十分保証することができます。
軽量で品質の安定した
製品が得られます
積層接着のため節などの欠点の分散度合いが高いので、材質のバラツキが少なく、また単板乾燥による含水率分布の均等化が容易であり、機械的性質にバラツキが少なく安定した品質の製品が得られる真の工業製品です。
製品が十分に
乾燥されています
製品は平衡含水率以下に乾燥されていますので、収縮による割れ裂けなどが生じません。
用途に応じてどのような
寸法でも製造可能です
単板積層数を増減することによって用途に応じたどのような厚さの製品でも製造可能です。また、幅、長さについては再割りすることができます。
防腐、防蟻、防虫などの
薬剤処理が容易です
防腐、防蟻、防虫処理などの薬剤処理を、単板または接着層に施すことにより、容易に行えます。
製造方法
LVLが生産されるプロセスは、原木、玉切り、単板切削、裁断、乾燥、接着、積層、切断などですが、これらの工程の多くは合板製造工程と同じです。そのため、LVLの製造工程には、既存の合板プラントを利用しますが、接着積層工程以降については専用プロセスを有するものがあります。大半は合板の製造機械設備を兼用していますが、近年、わが国でもLVL専用の新しいプラントが登場してきています。
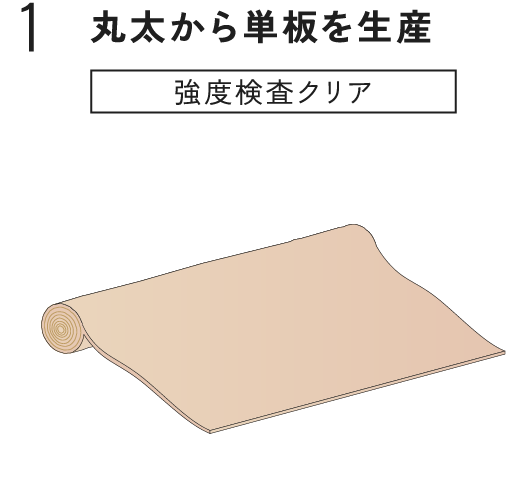
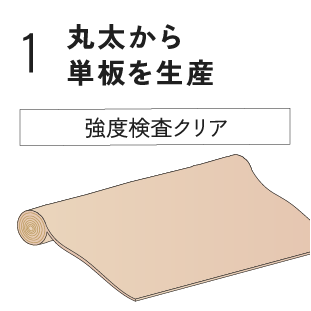
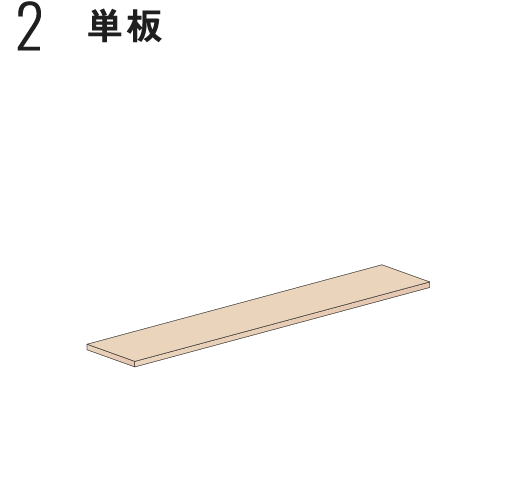
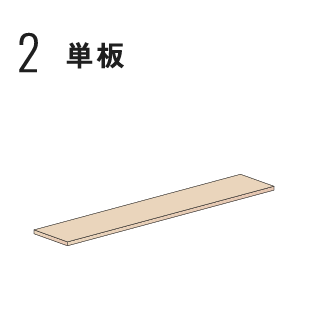
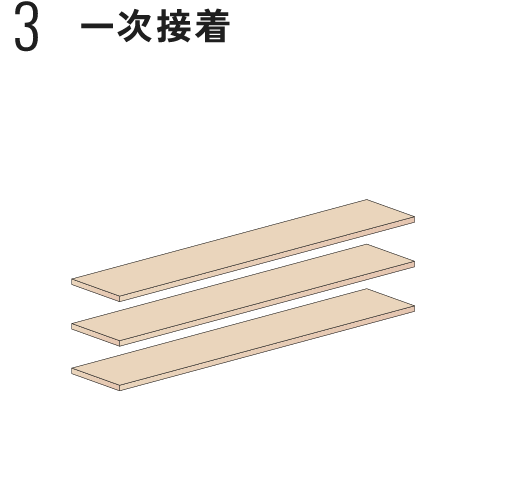
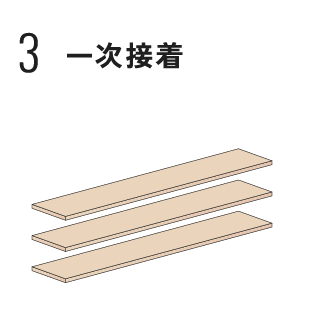
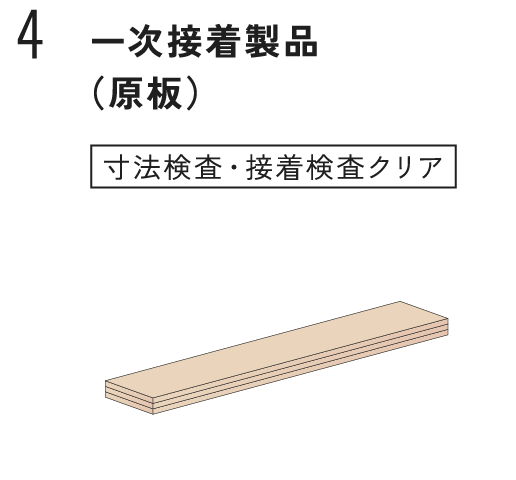
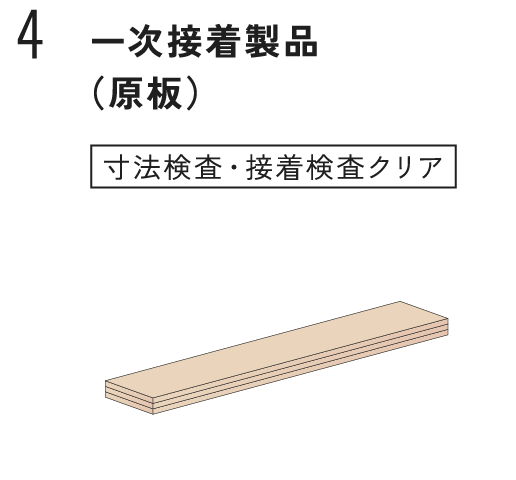

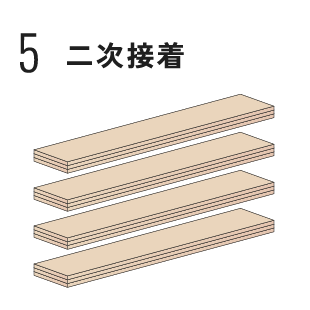
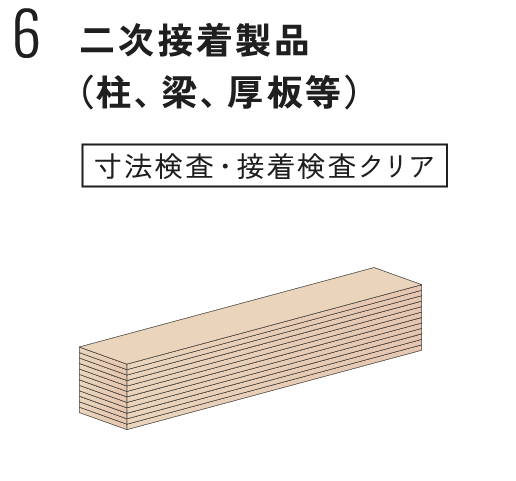
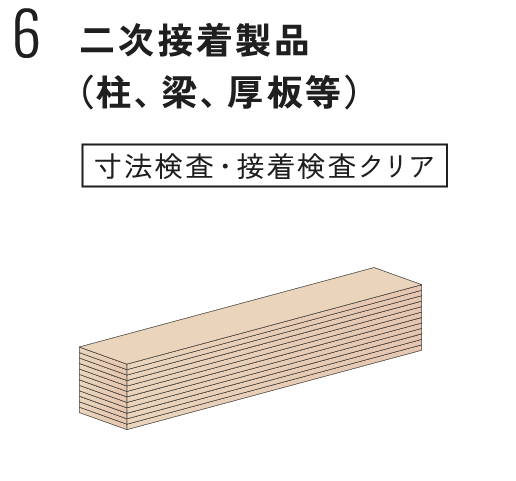


用途
LVLには多種多様な用途がありますが、現在使われている用途、あるいは近い将来使用される可能性のある用途を分類すると、次の通りです。
建築用
- 木造住宅建築用(構造材、造作材)
- 非木造住宅建築用(造作材)
- 産業建築用(倉庫、体育館、橋梁、畜舎)
- 建具用(ドア、窓枠、ブラインド)
- 仮設材料用(足場板)など
産業用
- 機械、設備(機械部品、タンク頬)
- 電気(家電部材、絶縁材料)
- 自動事(トラックの荷台、バスの床)
- 農業用(土木資材、機具の柄、畜力車)
- 鉄道(枕木)
- 船舶、漁業(船室、船倉、養殖器材)
- 航空機(室内装備)
- 輸送資材(パレット、梱包、コンテナ)など
日用品
- 家具(芯材、化粧材)
- 台所用品(まな板、食器、柄)
- 室内装飾品(時計、飾物)
- 文房具(筆記用具、彫刻具)
- 運動用具(ラケット類、ゴルフ用具)
- 音楽用品(ピアノ、オルガン、ギター)
- 身のまわり品(ボタン、ブラシ)など
歴史
LVLは決して新しい材料ではなく、古くは第二次世界大戦中の木製飛行機の部材として使用されたといわれています。工業用としては、昭和40年代に「平行合板」の名で生産が始まり、家具、建具、楽器、運動具など造作用として広く利用されるようになりました。このLVLが近年改めて注目されたのは、1972年米国林産試験場における構造用LVL開発プロジェクト研究の成果が発表されて、その合理的な製造システムにわが国の企業の多くが関心を示したからです。
このシステムでは、合板やパーティクルボードなどの製品に使用されている大型プラントを用いて高能率に生産することが可能だったので、大量生産・装置型の材料開発としてLVLが注目を集めたわけです。
この時期が、わが国の高度成長期と一致していたので、合板業界はプリント合板、コンクリート型枠用合板に次ぐ商品として、LVL開発に取り組みました。
しかし、石油ショックとそれに続く合板業界の構造不況、原木事情などの要因もあって、LVLの開発は大量生産・装置型というよりも高性能用途を狙う性能向上型、歩留まり向上による省資源型、熱効率の良いプラント開発を目指す省エネルギー型、未利用樹種や間伐材を原料とした材料開発に目が向けられました。
この間、昭和53年8月には建築物の耐力部材以外の用途を対象にした造作用としての「単板積層材の日本農林規格(JAS)」が制定され、品質を保証した製品が供給されるようになりました。
さらに、昭和61年5月には、米国政府および米国林産物業界がデモンストレーションハウスとして東京二子玉川に建設したサミットハウスに、LVLが耐力部材として用いられたことなどから、建築物の耐力部材としての性能面での良さが認識され、構造用としてのLVLへの関心が高まりをみせるようになりました。こうした事情を背景にして、昭和63年9月には「構造用単板積層材の日本農林規格(JAS)」が制定され、構造用LVLへの道が開かれたのです。
Q&A
-
A. 構造用LVLに使用されている接着剤は木材用接着剤の中でも最も耐久性に優れた接着剤を使用しています。また、接着工程は製造過程の中で最も厳しく管理されております。 一度完全に接着されたものは剥がそうと思っても剥がれるものではありません。
造作用LVLの場合は、濡れる場所での使用を想定しておりませんので、「濡れる・乾く」を繰り返すとはがれる可能性があります。 -
A. 構造用LVLに使われている接着剤はフェノール樹脂接着剤、レゾルシノール樹脂接着剤、水性高分子-イソシアネート系接着剤といいます。
これらは木材用接着剤の中でも最も耐水性、耐久性に優れた接着剤です。フェノール樹脂接着剤は熱を加えることで硬化するタイプの接着剤です。ホルムアルデヒドが樹脂の合成に使用されていますが、完全に硬化した後ではホルムアルデヒドが分解されて放出されることはありません。レゾルシノール樹脂接着剤は常温で硬化するタイプの接着剤で、主に二次接着(練り合わせ)に使用され、性能はフェノール樹脂と同等です。水性高分子-イソシアネート系接着剤は非ホルムアルデヒド系の接着剤ですが、耐熱性が劣るため高度な耐火・耐熱性能が求められない使用環境Cでのみ使用できます。
造作用LVLの場合は、合板の2類(タイプ2)相当以上の耐水性があればよいので、上記接着剤以外にもメラミン樹脂、ユリア樹脂などが用いられています。 -
A. 耐用年数は基本的に使用環境により異なり、常時湿った場所や屋外に暴露される環境など劣悪な環境下では木部が先に劣化してしまいます。常時乾いた環境であれば米国では100年間経過した建物の実績があります。構造用LVLに使われている接着剤は耐久性に優れており、耐久性の促進劣化試験では10年以上経過した物でも接着力の低下は極僅かになっています。
-
A. 構造用LVLに使われている樹種は主に針葉樹が使用されています。使用量の多いものではダフリカカラマツ(ロシア産)、ラジアータパイン、国産カラマツ、スギなどです。構造用LVLは曲げヤング係数区分になっており、樹種による区分はありません。これは強度さえしっかり保てればどのような樹種を使用しても良いことを意味しています。
造作用LVLの場合は、針葉樹、広葉樹問わずさまざまな樹種が使われています。多いものではポプラ、ラワンがあります。 -
A. 「たわみにくさ」の指標で、弾性率ともいって「荷重を掛けたときにどのくらいたわむのか」を表しています。ヤング係数が大きいほどたわみにくい材ということになります。
-
A. 住宅等の構造物の耐力部材として用いられるものを構造用LVLといいます。それ以外の部分で使用されるものを造作用といいます。構造用は強度に関する規定 が多い一方、材面の規定が1種類しかなく、また造作用は材面の等級が3等級に区分されているのに対し、強度に関する規定がありません。
-
A. 構造用LVL一般製材に比べかなり強くなっています。例えばベイマツ製材(1等)にくらべ構造用LVLの140E-525F(特級)では約1.7倍の強度 を持っています。これは105×300×3650の床梁1本にベイマツ製材(1等)では約3.2tまで耐えられるのに対し、同じ寸法の構造用LVLの 140E-525F(特級)では5.3tの荷重に耐えられることを意味しています。
-
A. 許容応力度とは、簡単に言えば、「これくらいの力まで持ちこたえます」という数値です。この値は計算上の話であり、実際にはもっと持ちこたえられます。構造用LVLでは、平成13年国土交通省告示第1024号により基準強度が定められ、この強度をもとに長期・短期の許容応力度を計算します。
-
A. LVL(構造用、造作用とも)は含水率が10%前後と完全に乾燥しています。そのため、使用しているうちに乾燥してやせてくることはありません。ただし、集成材、KD材と同様雨などで濡れた場合にはふくれてくる傾向にあります。保管される場合は水に濡れない屋根のある場所に保管してください。
-
A. 生物材料である木材の大きな特徴の一つに水分の吸・放湿性があり、これは生物材料がその組織内に水分を保有していることを意味しています。この水分の保有量を含水率といいます。木材では水分が放湿されると寸法が減少する(やせる)傾向にあります。
-
A. "AQ" とは "Approved Quality" の略称で、新しい木質建材等について品質性能等を客観的に評価・認証し、消費者に安全性及び居住性の優れた製品の提供を目的として(財)日本住宅・木材技術センターが認証しています。認証製品にはAQマークを表示しています。 JASは広く普及している製品を規格化しているのに対し、AQは新技術の開発による新製品について機動的に認証品目に加えると共に、需要者の要求性能の変化に応じた品質性能基準の見直しも行っています。
-
A. 燃えたときにダイオキシン等特に有害となる物質は発生しません。
-
A. 揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)と言います。すでにJASなどで厳しく規制されているホルムアルデヒドをはじめ、業界で自主規制されているトルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの4物質、建築基準法で使用が禁止された防蟻剤のクロルピリホスなどがこれに該当します。
-
A. LVLの寸法精度はJAS規格に基づいています。乾燥材ですので、水濡れによる膨張を除けば安定した寸法精度を持っています。
-
A. 製材、集成材よりも強く効きます。ただし、繊維方向がそろっているため、あまり端部近くに打つと割れることがありますのでご注意ください。
-
A. 他の木質材料と同様に手刻み加工ができます。
-
A. 専用の金物というものはなく、一般に広く流通する金物工法に対応ができます。
-
A. ツーバイフォー工法(枠組壁工法)につきましては、住宅金融普及協会発行の「枠組壁工法の構造設計―スパン表―」というスパン表がございます。
-
A. 断熱性能を計算する上で必要な熱伝導率は、
・カラマツLVL (密度 580 kg/m3) 熱伝導率λ 0.132 (W/mK)
・スギLVL (密度 497 kg/m3) 熱伝導率λ 0.117 (W/mK)
(熱伝導率はJIS A 1412-2 の評価方法に準拠して測定 )
次世代省エネルギー基準 (Ⅳ地域)において、木造住宅 (外張断熱工法又は内張断熱工法)の壁の断熱材に求められる熱抵抗値(m2・K/W)は、1.7(m2・K/W)で、カラマツで、225㎜、スギで199㎜以上厚みを確保していれば、LVLのみで基準を満たすことができます。 -
A. 結露しやすさの目安となる透湿抵抗の測定値は以下の通りです。
・カラマツLVL 透湿抵抗 Zp 0.0269 ((m2・S・Pa)/ng)
・スギLVL 透湿抵抗 Zp 0.0154 ((m2・S・Pa)/ng)
・ラジアータパインLVL透湿抵抗 Zp 0.0181 ((m2・S・Pa)/ng)
(透湿抵抗は JIS A 1324-1995 の評価方法に準拠して測定 ) -
A. 外壁にあらわしで使う際にはまだ耐候性に問題があります。庇を深くする、地面からの跳ね返りをおさえる等の工夫が考えられますが、今後より耐候性を高めるために、防水や塗料の開発が必要となります。
-
A. FRP防水、ポリカーボネートなどで保護、ガラス繊維塗料などが考えられますが、経年劣化の問題はあるため今後耐候性のある塗料の開発が待たれます。
-
A. LVLを室温20度相対湿度40%での平衡状態から、室温20度相対湿度90%に移行させた寸法安定性能検証実験では、重量変化率は5%、幅変化率は2%、長さ変化率は0.1%、厚さ変化率は1.5%程度となっており、カラマツ合板と同程度の値となっています。
東京の場合、気温は0~40℃、湿度は40~80%程度年間変動すると考えると、上記の値程度の季節変動が生じることになります。
設計時に、寸法変化をあらかじめ推測し、寸法変化に追従できる部材の納まりにしておく必要があります。 -
A. LVLt=100㎜厚壁の遮音等級はRr29です。 (JIS A 1419の評価方法により測定 )
遮音性について共同住宅の界壁で使用する際には、まだ十分な性能があるとは言えません。遮音性能が求められる箇所では、材料を厚くして使用するか、吸音材等と併用して使用してください。
遮音実験LVLt=100㎜厚壁を用いて3種の試験体で遮音性能実験を行いました。
試験体1:LVLt=100㎜
試験体2:LVLt=100㎜+目地ガムテープ張り
試験体3:LVLt=100㎜+片面石膏ボード2重張り
試験を行った結果、LVLt=100㎜の壁の遮音等級はRr29でした。目地部にガムテープを張った仕様もRr29とあまり性能が変わりませんでした。これにより、目地部の影響はさほど受けないという結果が得られました。
一方、片面に15㎜、21㎜の石膏ボードを2重に張った仕様はRr48という結果となり、遮音性が高い性能結果が見られました。石膏ボードの重量分と、LVLとボードにクリアランスを確保して設置したために十分な性能が得られたといえます。音は材料の重さ (密度)によって決まるため、いかに重量をかせげるかがポイントになります。しかし、LVL100㎜の上に石膏ボード15㎜と21㎜張りでは間仕切りとしては少し過剰な性能と厚みといえなくもないので、今後検討が必要です。
LVLだけではまだ十分な遮音性能が得られていないので、今後も性能を上げる方法を検討する必要があります。

構造用LVL 画像は、こちらからご自由にお使いください。
ご使用の際は「全国LVL 協会HP より引用」と必ず記載ください。

